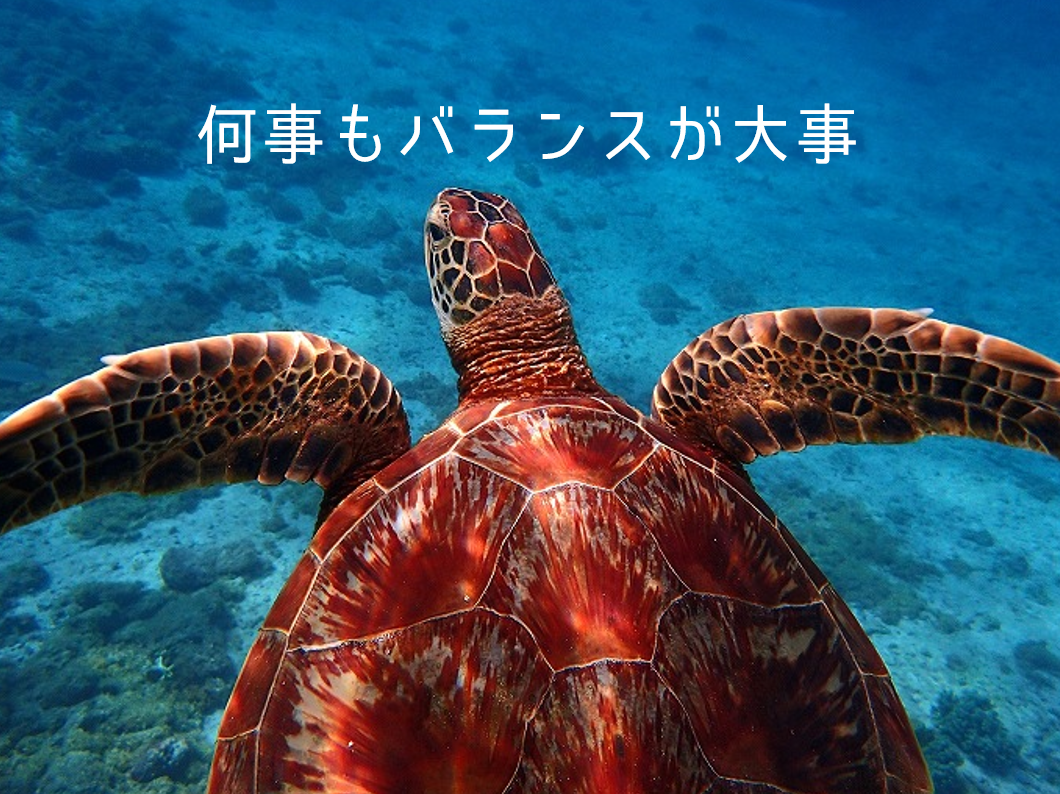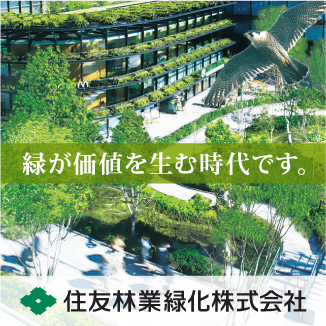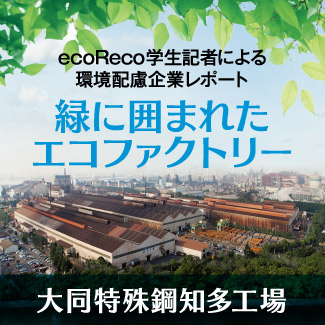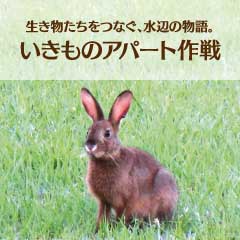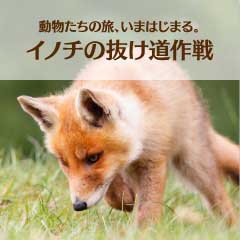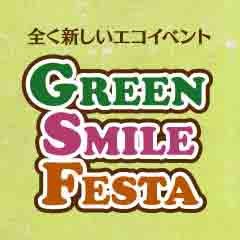【指標種のこと知って図鑑!】 vol.21 たぬき
皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪
今日は庭の木を剪定しました。
大きく育ってくれるのはうれしいですが、年々剪定が大変になっています…
まあ、それも庭造りの醍醐味ですけどね!!!
長い間手入れしないとすごいことになってしまうのでこれからも定期的に頑張ります!!!
さて、そんな今回はタヌキについてかいていきます。

皆さんにも なじみ深いタヌキさんは、企業緑地のなかでもたまに見ることができます。
また、日本のほかにもシベリア東部、朝鮮半島、中国東部にも分布しているので海外でも観測することができますよ!ヽ(*’0’*)ツ ワァオォ!!
さて、タヌキさんといえばよくアライグマさんに見間違えられますよね。
しかし、実は意外と簡単に見分ける事が出来ます。注目するべきポイントはしっぽです!!!
アライグマさんは尾に輪っか状の模様がありますが、タヌキさんにはありません (・ェ・。)ナルホドネ
皆さんもこれからはしっぽに注目してタヌキやアライグマを観察してみてください!!!
そんなタヌキさん実はイヌ科の動物だということを皆さん知っていましたか? Σ(゚□゚(゚□゚*)ナニーッ!!
他のイヌ科に比べてずんぐりむっくりしているので意外ですよね。
また、タヌキさんは“狸寝入り”や“狐と狸の化かし合い”など多くのことわざに登場します。
人間と昔から関わりが多かったことが想像できますね。
僕もタヌキに関することわざを作って有名になりたいです!
夜行性ですし、少し臆病なところがあるのでモニタリング中に観測することは難しいかと思いますが、ため糞くらいは頑張って見つけられるようにします!
発見した際はweb記事にも書くかもしれないので楽しみにしていてください!
それでは今回はこの辺で失礼します。
次回の「指標種のこと知って図鑑!」もお楽しみに!!!!!
画像出典 動物図鑑 タヌキ https://pz-garden.stardust31.com
大同大学 2年 丸井聡士
ヤンバルクイナの復活とロードキル
こんにちは!!事務局の神田です!
日に日に寒くなり、衣替えをしなきゃいけないと考えつつもなかなか実行できていません。
これから、インフルエンザも流行ってくる時期ですので、より手洗いうがいなどを徹底しましょう!!
沖縄にいるヤンバルクイナという鳥はご存知ですか?
国指定の天然記念物であるヤンバルクイナは、沖縄本島北部の国頭村,大宜味村,東村を合わせた「やんばる」という地域の森のみに生息しているほとんど飛べない鳥で、1981年に新種の鳥として発表されました。
そんなヤンバルクイナは1985年には1800羽発見されていましたが、一時期700羽まで減り、1991年には絶滅危惧種になりました。
その原因として、ハブを退治するために人間が持ち込んだ外来種のマングースや、こちらも外来種であり人間が持ち込んだイエネコによる捕食が大きく影響したと言われています。
ヤンバルクイナを復活させるために、マングースの行動範囲を狭める柵を設置したり、ネコには飼い主が分かるようマイクロチップの埋め込みや避妊・去勢手術を行うなどの対策が取られました。また、ヤンバルクイナの飼育繁殖も行なった結果、2014年には1500羽まで復活しました。
しかし、近年ではロードキルが頻繁に起こっており、2019年には31羽が交通事故に巻き込まれています。
ロードキルの対策として、ヤンバルクイナの絵が描かれているとび出し注意の道路標識が設置されたり、道路を通らなくても移動ができるように道路の下にアンダーパスというトンネルが造られましたが、なかなか効果が出ていません。
また、これはキツネの数が増えたことによってキツネのロードキルも増えてしまった知多半島の事例にも似ていますね。アンダーパスや生息地の開発回避などの対策を取っていくことで、彼らにとって少しでも住みやすい環境になると良いですね。

マツタケが絶滅危惧種に!!
こんにちは!!事務局の神田です🌼
最近は昼と夜の寒暖差が激しく、なかなか体温調節も難しくて悩んでいます(笑)
皆さんも風邪をひかないよう気をつけて下さい!!
今年7月にマツタケが絶滅危惧種になったことはご存知ですか?
マツタケが絶滅危惧種になった原因はいくつかあり、多くの要因を占めているのが、以下の2つです。
①マツクイムシによってアカマツの水を吸われ、枯れ、生育できる山が減った。
②里山のアカマツ林に人が入ることが少なくなり、アカマツとマツタケが成長しにくい環境になってしまった。
です。アカマツとマツタケは、枯れた土地が好みで、松ぼっくりや落ち葉を集めて燃料や肥料にしていた時代は、成長しやすいですが、落ち葉が積もって豊かな土地になると、アカマツは雑木に、マツタケは他の微生物に、負けてしまいます。
このようなことがあり、戦前に日本で採れていた1万2000トンものマツタケは、2018年には56.3トンになってしまいました。
近年では中国のマツタケを輸入することも多かったですが、今年はコロナウイルスの影響で多く輸入することが難しく、なかなか手に入りにくくなっているそうです。
今回のニュースをきっかけに里山文化を見直すことも大切だと思いました。
新しい技術などで暮らしやすい世界にしていくことも大切ですが、昔ながらの文化も大切にしていきたいです。

【指標種のこと知って図鑑!】 vol.19 ハクセキレイ
みなさん、こんにちは!
今回の【指定種のことを知って図鑑!】は日本の空をかわいく飛ぶ、ハクセキレイという鳥をご紹介します!!

ハクセキレイという鳥の名前を聞いたことがないという人も多いと思います。
僕なんかは最初、虫の名前かと思っていました(;^ω^)
しかし、みなさんの中で川や田んぼの近くで白と黒の小鳥を見たことはありませんか?
その鳥こそがハクセキレイなのです!!
体長は21 cmほどで白と黒の体色、そして長い尾羽が特徴的です。
日本各地の海岸、河川、池沼など水辺が好きですが、農地、駐車場、道路といった場所にも住んでいます。
実は、みんなの身近なところにいるんですね!!
雑食でクモやガといった虫やミミズが主なエサですが、パンくずを食べる姿も確認されています。
イネやワラで作った皿状の巣で、5~7月に1回に4~5個の卵を産み、雛は13~16日で巣立ちします。
巣立ちした後も親鳥と行動するので仲良く4羽ほどで集まっていることが多いです!!
こんなかわいい見た目とは裏腹に縄張り意識が強く、特に冬にはハクセキレイ同士で追いかけまわしたり、攻撃しあったりして生活する場所を奪い合っている様子が見られます。
でも人間にはとても懐いていて近くまで寄ってきたり、人の手から直接餌をもらったりすることもあります!
でも餌付けはしちゃだめだから他の野生動物にも餌をあげないように気をつけましょう!
ちなみにハクセキレイは幸運を運ぶとも呼ばれとても縁起がいい鳥でもあります。
「チュチン、チュチン」
という鳴き声がしたら近くにいる鳴き声なのでぜひ探して見てください!
地上で羽を広げて求愛ダンスをしている姿が見られたらほんとに運がいいです!!
以上ハクセキレイについてでした!!
最後まで読んでくれてありがとうございます!!
また次回の【指定種のことを知って図鑑!】で会いましょう。さようなら~
中部大学 2年 三宅航世
《画像出典》
https://zukan.com/media/leaf/original/107081.jpg?width=832&height=624&type=resize
ストローで環境が変わる?
こんにちは!!事務局の神田です🍁
9月もあっという間に終わってしまいますね😢
先日、ショッピングセンターでお買い物をしていたら、「環境保護のための『プラスチック製ストロー』削減の取り組みについて」というポスターを発見しました。
ポスターには、このショッピングセンターでは、一部店舗を除きプラスチック製のストローを常備しないということが記載されていました。
スターバックスコーヒーでは紙ストローが導入されていますが、紙ストローにすることでどのような効果があるのでしょうか。
現在多く使われているプラスチックストローは、耐久性も良く値段も安いですが、海に流れてしまうと微生物に分解されることはない為そのまま海に残り海洋汚染の原因になってしまいます。そして、そのプラスチックを間違えてクジラなどの大型生物が食べてしまい死んでしまい生態系にも影響が出てしまいます。
小さい魚もプラスチックから悪影響を受けており、マイクロプラスチックという微小のプラスチックゴミには有害物質が付着していることがあり、それを小さな魚が飲み込み、他の生き物がその魚を食べることにより生態系に影響が出ることもあるそうです。
しかし、紙ストローは海に流れてしまっても分解されるので環境への悪影響が少ないそうです。
紙ストローについて使い心地が悪いなどありますが、これから日本で普及していくことが増えるそうなので慣れていく必要があるかもしれません。
ストローは日常で多く使用するため、紙ストローを使用することで環境について意識する機会が増えそうですね!!

ニホンカモシカとシカの関係
こんにちは!事務局の神田です☁
すっかり秋らしく過ごしやすい気候になりましたね!!
いま、九州(熊本・大分・宮崎)に生息する特別天然記念物のニホンカモシカが減少していることはご存知ですか?
二ホンカモシカは、東北地方から中部地方・四国・九州に生息していますが、九州の個体のみ大幅に減少してしまっているそうです。
1994年~95年度には九州三県で約2200頭いたカモシカも、2018年~2019年度には200頭まで減少してしまいました。
二ホンカモシカが減少した理由として、1990年代以降、彼らの生息地である山岳地帯が減少したことや、狩猟者の減少、森林伐採をし草地化したことにより鹿が増加し、ニホンカモシカの生息範囲が圧迫されてしまったことなどが原因と考えられています。
縄張りから追い出されてしまったニホンカモシカは、標高の低い里山へ身を移しました。しかしそこには、農作物を荒らす鹿への対策として罠が仕掛けてあり、その罠にニホンカモシカがかかることが増えたそうなんです。また、野生のタヌキとの接触が増え、タヌキが持つ疥癬(かいせん)という皮膚病に感染してしまったことも減少の理由と言われています。
さらに、生息地が分散してしまった為、異性と出会う場が少なくなったこと要因の一つとされています。
絶滅を回避するために鹿を減らしニホンカモシカの生息環境の回復を狙うことも考えられているそうですが、生態系のバランスを十分に考慮しないと思いもしないところに悪影響が出ることも考えられます。慎重に判断する必要があると思いました。

新型コロナウイルスによる環境の変化
こんにちは!!事務局の神田です☀
コロナウイルスの感染者数が少しずつ減少傾向にあるようですが、まだ油断は出来ない状態ですね。
コロナウイルスによるロックダウンが行われたり、緊急事態宣言が出て、自粛やステイホームに徹したことは、どなたの記憶にも新しいと思います。しかし・・・ステイホーム期間中は、外出ができずにフラストレーションがたまったり、友人や大切な人に会うことができずにさみしい想いをしたりと、良いことなど何もない!というイメージですが、自然環境には良い影響があったようです。
例えば、ロサンゼルスでは空気が澄んだことにより今まで見えていなかった遠くの雪山が見えるようになったり、ヴェネツィアでは、濁っていて何も見えなかった水路が透き通り魚の泳ぐ姿が見られるようになったりしたそうです。
日本では2019年の3月~6月と比べ、2020年の3月~6月のほうが空気が綺麗だったというデータも発表されており、経済活動が止まるとこんなにも環境に変化があることが分かりました。
長年問題視され続けてきた環境問題が、人間の移動や経済活動が止まることで、こんなにすぐに改善されたという事実には非常に複雑な気持ちになりますね。
とはいえ、経済活動を完全に止めてしまっては、私たちの文化的な暮らしを維持することはできません。人類がコロナウイルスに完全に打ち勝ったあと、経済活動と、環境保全のバランスをどうとっていくのか、じっくり考えていきたいですね。

コウノトリの自然繁殖
こんにちは!!事務局の神田です!
まだまだ暑いですが、8月もあっという間に終わりますね!
コロナウイルスも一時期よりも減少傾向にあると発表され一安心ですが、気を抜かずにしっかりと対策をしましょう!!
嬉しいニュースです!東日本で初めて野外繁殖にてコウノトリが巣立ちました!!
国の特別天然記念物でもあり、赤ちゃんを運ぶという言い伝えでも有名なコウノトリ。
昔は日本各地にいましたが、明治時代以降乱獲や環境汚染で減少し、
1971年には野生のコウノトリは絶滅してしまいました。
そこで、コウノトリの人工繁殖の歴史を紹介します。
1965年には野生のコウノトリが12匹まで減ったため、2匹を捕まえ、兵庫県豊岡市のコウノトリの郷公園を中心に人工飼育が開始されました。
1985年には、ロシアからコウノトリの幼鳥6羽を受贈します。
1989年には、ロシアから受贈したコウノトリが飼育下繁殖に成功し、それ以来毎年、増殖に成功し現在は約100羽のコウノトリが施設内で飼育されています。
2005年からはコウノトリ野生復帰に向けて放鳥が開始され、
2007には日本国内の野外では43年ぶりにヒナが誕生し、46年ぶりに巣立ちました。
以後毎年野外で繁殖しています。その結果今では野生のコウノトリは217羽まで回復し、全47都道府県への飛来も確認されたそうです。
そして、栃木など4県にまたがる渡良瀬遊水地でコウノトリが自然繁殖で2羽生まれ、この夏、巣立ちました。
これから人工繁殖が必要のないくらいにコウノトリが復帰してほしいと思います。
命をつなぐPROJECTのYoutubeに挙がっている「知多半島生態系ネットワークフォーラム2019」でもコウノトリについて話されているのでぜひ下のリンクから観て下さいね!!
https://youtu.be/XFLEXnsV70w

絶滅危惧種のアオウミガメが急増!?
こんにちは!事務局の神田です!!
最近、絶滅危惧種のアオウミガメが高知県室戸市の定置網に入り込んでしまっていることが急増しているそうです。
アオウミガメは、小笠原諸島や屋久島に産卵のために上陸するのですが、小笠原諸島ではウミガメを食べる文化があり、臭みの少ないさっぱりとした赤身は刺身やお寿司として食べられてきました。
しかし、個体数が減少し絶滅危惧種に指定されると、捕獲数制限が設けられるなど、保護が進められてきました。
小笠原諸島では年間に135頭までの捕獲が許されています。
こうした保護活動が功を奏したのか、アオウミガメの個体数は徐々に増加に転じ、定置網に入っていることが増えました。
一年間で定置網に入りこんだアオウミガメの数は、去年で79匹、過去最多の2006年で103匹。今年はそれを大幅に超え7月までで150匹まで増えています。
一時は絶滅しそうだったアオウミガメが戻ってきていることは、とても嬉しいニュースですね!ただし、アオウミガメは海草を餌にしているため、今度は逆に海草が減ったり、アオウミガメを狙うイタチザメといった危険な生き物が増えることも考えられます。
絶滅危惧種が増えることは嬉しいですが、生態系は微妙なバランスの上に成り立っているものなので、今後どういう影響が出るのか、慎重に見極めていきたいですね。

【指標種のこと知って図鑑!】 vol.17 オオカマキリ
みなさん、こんにちは!
今回の『指標種のことを知って図鑑!』は日本中の草むらで見かけるオオカマキリについてご紹介します!
みなさん一度は、草むらや公園でカマキリを見かけたことがあるのではないでしょうか。
日本国内には数多くのカマキリが生息していますが、その中で最も知名度が高くてよく見かけるのがオオカマキリなのです!
オオカマキリは、名前の通りとても大きいカマキリです。
最大でオスは9 ㎝、メスは10 cmほどまで成長し、南にいけばいくほど大きなサイズになるそうです!
この種はオスよりメスのほうが基本的に大柄であり、交尾中にメスがオスを食べてしまうこともあるのです!!!
このオオカマキリは緑地モニタリング中に出会ったオオカマキリです。
7~8 ㎝ほどあり、その大きさに驚きましたがもっと大きな個体がいると想像するとワクワクしますよね!!

また、体色は緑色個体と褐色個体の2種類でありこのオオカマキリは緑色個体です。
体色は成長するとその違いが明白になり、これは運によって決まるため、背景の色によって体色を自由に決めているわけではないそうです。
体色を変えられると勘違いしてしまうのは、草むらでは褐色個体が鳥などの天敵に見つかりやすいため、
緑色個体が繁殖しており、草むらの中では緑色の個体をよく発見するためであるといえます。
辺りが茶色いところ場所で褐色個体が多いのも、これと同じです。
ところで、みなさんはオオカマキリに対してどのような印象を持っていますか?
私は、攻撃的で積極的に狩りをよくしている印象でした。
しかしそれは異なり、オオカマキリの狩りは完全なる待ち伏せ型です。
草木や花の陰に隠れたり、樹液に集まる昆虫をすぐそばで待ち伏せ、射程圏内に入った獲物を大きなカマでがっちりと捕獲するのです!バッタやチョウはもちろんカエルやトカゲなどの両生類を捕食することもあるそうです!
以上オオカマキリについてでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
また次回の記事もお楽しみに!
中部大学 二年 遠島康生
綺麗な海・汚い海の違い
こんにちは!!事務局の神田です!
猛暑日が続いていますが、いかがお過ごしですか?
私は先日、愛知の海に海水浴に行ってきたのですが、やはり海があまり綺麗ではなくて😢
なぜ日本の海は水が濁っている場所が多いのでしょうか?
理由は大きく分けると3つあります。
1つ目に、プランクトンが多いことが挙げられます。
プランクトンが多いと海水が太陽光を反射しない為、海が濁って見えてしまうそうです。
また、日本の海に海藻が多いのもプランクトンが原因と言われています。プランクトンが多い海は汚く見えがちですが、実は栄養がたっぷりなので、美味しい魚が獲れます。その為日本の海鮮は美味しいんですね!!
2つ目に、サンゴがいないことが挙げられます。
沖縄の綺麗な海の底にはサンゴがいるというイメージの方も多いのではないでしょうか?
沖縄の海が綺麗な理由は、サンゴがいることも影響しています。サンゴは海の中で光合成を行い、二酸化炭素を吸い酸素を吐き出すと同時に浄化作用のあるミネラルを出す為、海が綺麗なんです!
3つ目に、生活排水の汚さが挙げられます。
現代では工場からでる産業排水はだいぶ対策がされていますが、家庭から出る生活排水がそのまま流れている地域もあります。
生活排水が処理されないと、川や海が汚れるだけでなく、生き物が生きていけなくなってしまいます。そうすると、生態系が崩れてしまう原因にもなります。
私たちがすぐに出来る対策として、生活排水を少なくすることが出来ます!
シャンプーや洗剤を多く使いすぎない、洗濯はお風呂の水を使うなど一人一人が心がけていけば、水質の向上に繋がると思います。
私は今までゴミの分別は意識していましたが、生活排水に関しては何も考えずに生きてきたので、これをきっかけに意識していきたいと思います🐬

【指標種のこと知って図鑑!】 vol.16 アブラゼミ
みなさん、こんにちは。
今回は、代表的なセミの種類であるアブラゼミについてご紹介します!
アブラゼミは主に森林で暮らしていますが、公園や街中にも多く生息しています。
そのため、夏には一番よく目にするセミではないでしょうか。
アブラゼミの名前は、漢字で「油蝉」と書くように、
「ジー―――」や「ジリジリジリ」という鳴き声が油の跳ねる音に聞こえることや、ハネが油に濡れた茶色のように見えることに由来しているといわれています。
世界には3,000 種ほどのセミがいます。
ほとんどのセミはハネが透明で、アブラゼミのように不透明なハネをもつセミは珍しいです。
日本ではなじみのある不透明で茶色のハネは、世界的に見るとアブラゼミの大きな特徴になるのです。
アブラゼミの幼虫は、木の根から養分をもらいながら5,6年ほど土の中で過ごします。
成虫の期間は1週間とされていましたが、生息環境などで個体差があり、長く生きるアブラゼミでは1ヶ月も生きることがわかっています。
少し涼しさを感じ始めた9月初め、「セミの声も減ったな・・・。」と思っていたとき、
「ジー―――」と足元で鳴いているアブラゼミを見つけました。

アブラゼミは、黒い眼をもちますがこの写真のアブラゼミは赤い眼です。
黒い澄んだ目は歳をとり老化すると目の色が濁り赤くなるため、遺伝的に赤い目をもったためといった理由が考えられます。
私は赤い目をしたアブラゼミをこの時初めて見たので、思わず写真を撮っていました!
みなさん、夏にアブラゼミを見かけた際には、そっと近づいて目の色を見てみてください。
赤い目をしたおじいちゃんゼミが鳴いているかもしれません。
以上、アブラゼミについてでした。
今回、アブラゼミをご紹介するにあたり私自身改めてアブラゼミについて知ることができました。知っていると思っていても、私達が見ているのは一部分だけかもしれないなと思いました。
ここまで見て下さりありがとうございました。
また次回の記事もお楽しみに!
人間環境大学 2 年 岡田 美夢
こんにちわ! 命をつなぐプロジェクトです。 すっかりブログの更新が滞っておりましたが、 命をつなぐプロジェクトは、FacebookやInstagram、YouTubeチャンネルで最新の活動状況を発信中です! ブログの更新 […]
続きを見る
こんにちは! 指標種のこと知って図鑑!のコーナーです(๑´ω`ノノ゙👏🏻 今回はナミアゲハをご紹介します( ˊᵕˋ ) さて皆さんはナミアゲハってどんな蝶か思い浮かべられますか?? ピンと来ない人もいるでしょう、では写真 […]
続きを見る
皆さんこんにちは! 今回の『指標種のことを知って図鑑!』はモンシロチョウについて解説していきたいと思います! 小学生だった頃に授業の一環でモンシロチョウを幼虫から成虫になるまで育てたのは懐かしい思い出です(*^▽^*) […]
続きを見る
皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 今日は庭の木を剪定しました。 大きく育ってくれるのはうれしいですが、年々剪定が大変になっています… まあ、それも庭造りの醍醐味ですけどね!!! 長い間手入れしないとすごいこと […]
続きを見る
皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ 部屋の掃除をしないといけないのはわかっているけれど、面倒くさいからやりたくない。 そんなことを毎日のように思っている丸井君です。 掃除をすぐに実行することのできる魔法を知って […]
続きを見る
こんにちは!!事務局の神田です! 日に日に寒くなり、衣替えをしなきゃいけないと考えつつもなかなか実行できていません。 これから、インフルエンザも流行ってくる時期ですので、より手洗いうがいなどを徹底しましょう!! &nbs […]
続きを見る
こんにちは!!事務局の神田です🌼 突然ですが皆さんはパンダを見たことはありますか? 日本では、パンダがいる動物園は3施設しかなくパンダは希少なイメージがあります。 そんなパンダは、1970代に起きた竹の一斉 […]
続きを見る
こんにちは!!事務局の神田です🌼 最近は昼と夜の寒暖差が激しく、なかなか体温調節も難しくて悩んでいます(笑) 皆さんも風邪をひかないよう気をつけて下さい!! 今年7月にマツタケが絶滅危惧種になったことはご存 […]
続きを見る
みなさん、こんにちは! 今回の【指定種のことを知って図鑑!】は日本の空をかわいく飛ぶ、ハクセキレイという鳥をご紹介します!! ハクセキレイという鳥の名前を聞いたことがないという人も多いと思います。 僕なんかは最初、虫の名 […]
続きを見る
こんにちは!!事務局の神田です🍁 9月もあっという間に終わってしまいますね😢 先日、ショッピングセンターでお買い物をしていたら、「環境保護のための『プラスチック製ストロー』削減の取り組みについて」というポスターを発見しま […]
続きを見る
皆さんこんにちは(。・ω・)ノ゙ コンチャ♪ マンガを買い始めてから早1年。 家のなかにもかなりマンガが増えてきました。片付けなければ... 新しいマンガを買おうと思っているので、おすすめのマンガがある方は是非教えて下さ […]
続きを見る
こんにちは!事務局の神田です☁ すっかり秋らしく過ごしやすい気候になりましたね!! いま、九州(熊本・大分・宮崎)に生息する特別天然記念物のニホンカモシカが減少していることはご存知ですか? 二ホンカモシカは […]
続きを見る